卒後鍼灸手技研究会 2018.5月
卒後鍼灸手技研究会に参加させて頂きました。
講師は、新美和子先生
東京医科歯科大学歯学部付属病院ペインクリニック外来
歯科医である先生自ら、ペインクリニック外来で鍼治療をしておられます。
今研究会では、
「頭頸部・顔面部痛に対する東洋医学的治療の概要」
というテーマでのお話でした。
ペインクリニック外来で、
対象としている疾患・症状・様々な治療方法のお話、
その中で鍼の適応疾患・適応範囲についてのお話がありました。
痛みの分類に即したご説明の中で、
①侵害受容性疼痛(炎症性疼痛、NSAIDsが効く、ズキズキ痛いと表現される)
この中で、筋筋膜性疼痛・筋痛に鍼が効くと。
②神経障害性疼痛(神経損傷に伴う痛み、発作性の痛み、ビリビリ電撃様痛と表現される)
この中で、ファーストチョイスではないが、三叉神経痛・三叉神経麻痺に鍼治療で対応しているものがある。と
③非器質的疼痛(上記2つ以外の疼痛、除外した後に残るもの)
この中で、持続性突発性疼痛などに、鍼治療で対応しているものがある。と
痛みの定義についても、噛み砕いて伝えて下さいました。
1986年 IASP国際疼痛学会
「痛みは、実質的または潜在的な組織損傷に結びつく、あるいはこのような損傷を表す言葉を使って述べられる不快な感覚・不快な情動体験である。」
「痛い」という感覚の経験と、「やだな」という感情が湧いてくる経験を分けて表現している。と
痛みは改善しているにもかかわらず、不快な情動体験が残ってしまう患者様がおられる。と
そんな患者様には、治療が新たな痛みの感覚にならないように極力注意する必要がある。と
今までの痛みの経験を良く聞いて、その患者様の感じ方の傾向を予想すると、
無理が起こりにくいのではないかとも仰っていました。
痛みを扱う臨床現場では、治療のゴールは患者様の痛みの消失である。と
つまり、患者様の感じ方次第・言葉次第という側面がある。と
痛みは患者様本人にしか分からないもので、患者様は痛みの中で生活しておられる。と
継続治療の経過では、
「どの位痛みが減ってきているかを評価してもらうようにしている」とのことでした。
ペインクリニック外来で、
心を砕いて診療に当たられているご様子を、
臨場感を持って話して下さいました。
研究会では、講義の後、実技もご披露下さいました。
口腔内からの触診のポイントや、
サージカルテープを用いた鍼通電の工夫など、
大変興味深く、勉強になりました。
参加させていただいて、良かったです(*^^*)
ありがとうございました。


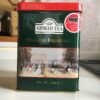
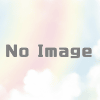

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません